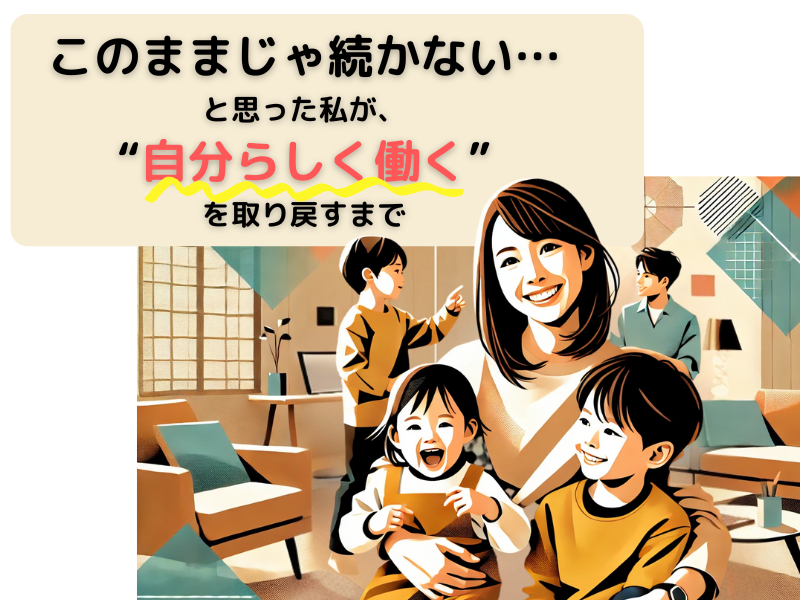子育てと仕事、毎日の家事。ルーティーンで同じことの繰り返し。
自分の感情はどこへ?自分のしたいことってなんだったっけ?
笑っていない?眉間いシワばかりよっている・・・・
このような悩みを持つ方へ、10年間、子育て・家事・仕事など時間に追われていた子育て主婦の私が、子育て仕事をうまく両立できたことをが、本音ベースで語ります。
この記事を読めば「子育てと仕事の両立をするためにどうしたら良いか?」の体験談が知れて、
自分らしく充実した生活を送るための意識づけや働き方が見つかります。
良い母、良い妻でいようとばかり考えなくても良いんです。



この記事を読んでいるあなたは、きっと何かを変えたいと思っているはず。気づいたその時が、働き方や思考見直す良きタイミングです!


- 40代3兄弟の母
- 子育てしながらリトミック講師10年
- 在宅ワーカー3年働き方を試行錯誤
- 自分時間はピラティス&ヨガ&テニス
- 私の詳しいプロフィールはこちら
子育てと仕事、うまく両立してるはずなのに…なぜか疲れがとれない理由3つ


「子どもも元気。仕事もちゃんと行けてる。家事もなんとか回せてる……
それなのに、なんでこんなに疲れてるんだろう?」
そんなふうに感じたことはありませんか?
“何も問題ないはず”なのに、どこか心と体がしんどい。
そう感じるのは、あなただけではありません。
ここ記事では、そんな「理由の見えにくい疲れ」の正体について紐解いていきます。
- 見た目の“両立”と、内側の“すり減り”は別もの
- 「忙しさ=充実」ではない
- 「がんばり屋さん」ほど疲れを感じにくい
理由①:見た目の“両立”と、内側の“すり減り”は別もの
表面的にうまくやれていても、心や体は確実に疲弊しています
タスクはこなしていても、「休む」「自分の感情に目を向ける」時間が不足しているからです。
子育てやパートの仕事は、常に誰かのために動いている状態です。
「こなすこと」はできても、それが“自分に優しくできている状態”とは限りません。



私の場合、むしろ「できているから大丈夫」と思い込んで、
疲れを見過ごしてしまうことも多々。
これが疲労の蓄積につながり、あまり疲れてないはずなのに
夜すぐ寝てしまうってこともあります。
理由②:「忙しさ=充実」ではない
常に予定が埋まっている状態は、心の余白を奪います。
スケジュールがいっぱいだと、自分の感情や疲れに気づく余裕すらなくなるからです。



「忙しい=役立っている」と感じると、
一時的に満たされるかもしれませんが、
それは“頑張ることで安心を得ている状態”。
それが続くと、やがて「私って何のために働いてるんだっけ?」と
いう違和感がじわじわと広がっていきます。
理由③:「がんばり屋さん」ほど疲れを感じにくい
“まじめに頑張る人”ほど、無理を見逃しやすい傾向があります。
「自分はまだ大丈夫」「もっと頑張っている人がいる」という思考が、
疲れを正当に評価することを妨げるからです。



特に子育て世代の女性は、「家庭も仕事も大事にしたい」と
思うあまり、気づかぬうちに“限界の手前”まで
動き続けてしまうことがあります。
それは美徳ではありますが、持続可能ではありません。
「疲れたと感じてから休む」ではなく、
「疲れないように働き方を見直す」ことが必要です。
時間が足りないと感じるのは、“無意識の消耗”が多すぎるから





「気づけば1日が終わっていた」「今日も何もできなかった」——
そんな日々が続くと、「私は時間の使い方が下手なのかな?」と
落ち込んでしまうこともありますよね。
でも、実は“時間が足りない”と感じる背景には、気づかないうちに自分をすり減らしている
“無意識の消耗”が隠れているのです。
1日の中には“見えないタスク”が山ほどある
私たちが疲れるのは、実際のタスク量よりも「無意識にこなしている小さな動き」の積み重ねが原因です。
準備・気遣い・子どもの感情のケアなど、「やったことリストに残らない仕事」があまりにも多いからです。



たとえば、子どものお迎えに行く前に何時に出ればいいか計算して、靴下を探して、傘を準備して……
これらは小さな作業ですが、脳も体も確実にエネルギーを使っています。
記録にも残らず評価もされにくい「名もなき家事や育児」が、時間と心のゆとりを奪っているのです。
思考の“スイッチ切り替え”だけで疲れてしまう
育児と仕事の両立では、“役割の切り替え”だけでも大きなエネルギーを消耗します。
私たちは、子どもと接する「母」と、職場での「働く自分」とを瞬時に切り替える必要があるからです。
職場でパートの顔、家ではお母さんの顔。様々な顔を日々持っている私たち。



たとえば「仕事でクレーム対応をした直後に、笑顔で夕飯を作る」というような、極端な切り替えが当たり前になっています。
この切り替えは無自覚に脳に負荷をかけており、「なんだかクタクタ」という感覚につながっています。
意識しないと「疲れの原因」がわからない
“時間が足りない”と思ったときこそ、
まず「なににエネルギーを使っているのか」を見直す。
見直さない限り、同じルーティンで同じように疲れる毎日が続いてしまうかもしれません。



たとえば通勤の往復1時間や、必要以上に丁寧すぎる家事など、削れるところを見逃していることも少なくありません。
一度、自分の1日の流れを“エネルギー消費の視点”で見直してみると、
「この時間、無意識に使ってたな」と気づけるはずです。
柔軟な働き方ってズルじゃない。「私に合う形」を選んでいい理由5つ





「在宅ワークに切り替えたい」「パートの回数を減らしたい」
——そう思っても、「甘えてると思われないかな」「周りはちゃんと働いてるのに」と、自分にブレーキをかけてしまう人は多いものです。
でも本当に大切なのは、「自分にとって無理なく続けられる働き方かどうか」。
ここでは、柔軟な働き方を選ぶことがなぜ“ズル”でも“逃げ”でもなく、むしろ大切な選択なのか、その理由を5つご紹介します。
- フルタイムじゃなくても社会とつながれる
- 子どもの成長に合わせて働き方を変えていい
- 通勤ゼロ=余白が生まれる
- 働き方は“正解”より“相性”が大事
- 柔軟に働くことで自己肯定感も上がる
理由①:「フルタイムじゃなくても社会とつながれる」
働く形が変わっても、社会とのつながりは持ち続けられます。
今は、短時間・在宅・週数回など、多様な働き方が受け入れられる時代です
スキルを活かした業務委託や在宅ワーク、副業OKの企業など、選択肢は確実に増えています。
“つながり=フルタイム勤務”という思い込みを外せば、
自分のペースで社会と関われる方法はたくさんあります。
理由②:「子どもの成長に合わせて働き方を変えていい」
働き方はライフステージに合わせて柔軟に変えてOKです。
子育てのフェーズによって必要な時間・エネルギーの配分は大きく変わります。



私は、子供3人が未就園児から小学生の間は子供と一緒に働けるリトミック講師をメインに活動し
子供の成長とともに10年続けたリトミック講師を卒業し次のステップへ進みました。
未就園児がいる時期と、小学生になってからでは生活のリズムも余力も全く違います。
ずっと同じ働き方に固執せず、「今に合った働き方」を選ぶことはむしろ賢い選択です。
理由③:「通勤ゼロ=余白が生まれる」
在宅勤務や近所での仕事に切り替えるだけで、1日が驚くほどラクになります
通勤時間の削減は、時間・体力・精神的なゆとりを生み出します。
例えば往復1時間の通勤をなくすと、年間240時間(週5日×月20日×12ヶ月)もの時間が浮きます。



この時間があるだけで、朝の支度がゆっくりできたり、子どもの送迎にも余裕が持てるようになります。
理由④:「働き方は“正解”より“相性”が大事」
他人と同じ働き方を選ぶことが、必ずしも自分にとっての最適解とは限らない
性格・家庭環境・エネルギーの使い方は人それぞれ。
周囲がフルタイムでも、あなたには「午前中だけ働く」が合うかもしれません。



「週3×在宅」のように、自分の生活と心に合う形を見つけることが、無理なく続けるカギです。
理由⑤:「柔軟に働くことで自己肯定感も上がる」
無理をせず働けることで、自己肯定感や充実感が高まる
疲れやストレスを減らすことで、日々の満足度が上がり、自分の選択に自信が持てるようなります。
「できなかったこと」に目がいきがちな多忙な毎日から、
「今日はここまでできた」と思える余裕が生まれれば、自然と自分にやさしくなれます。



それが結果的に、家族や周囲にも良い影響を与えるのです。
私が“自分時間”を増やすために手放したものと、取り入れた工夫5つ


「自分の時間がほしいけど、毎日やることが多すぎる…」
そう思いながらも、なんとなく日々をやり過ごしている人は多いのではないでしょうか。
実は、「すごいこと」をしなくても、自分時間は生み出せます。



ここでは、私自身が実際に試してみて効果があった「手放したこと」と「取り入れたこと」を、あわせて5つご紹介します。
- 「全部自分でやらなきゃ」を手放した
- 「完璧な家事」をやめた
- 「スケジュールに“空白”を入れる」を取り入れた
- 「在宅や副業など、新しい選択肢を知る」を取り入れた
- 「家族のタスクを“見える化”して分担」を取り入れた
工夫①:「全部自分でやらなきゃ」を手放した
家事や育児を“自分だけで完結させる思い込み”をやめました。
頼れる部分は頼ることで、時間と心の余裕が生まれました。
例えば、洗濯物を夫に干してもらう。子どもにおもちゃを片付けてもらう。
完璧じゃなくても「任せる」を増やすことで、自分だけで背負っていた時間の負担が軽くなります。



最初は気になるかもしれませんが、「自分の時間をつくるため」と思えば気持ちも切り替えやすくなります。
工夫②:「完璧な家事」をやめた
家事を“丁寧に完璧にこなすこと”よりも、“まあOK”のラインを決めました。
力の入れどころを調整することで、気持ちの消耗が減ります。
例えば「掃除は週に1回まとめて」「食器洗いは夜まとめて1回」など、自分で“最低限ライン”を決めておくと、日々のプレッシャーが激減します。



清潔・安全が保たれていればOK。
何より、自分がラクになることを優先していいのです。
工夫③:「スケジュールに“空白”を入れる」を取り入れた
「何もしない時間」を意識的にカレンダーに確保しました。
空白の時間があることで、心のリズムが整いやすくなります。
1日の予定が詰まりすぎていると、予期せぬ出来事(子どもの発熱など)に対応できず、
パンクしてしまいます。



あえて“バッファ”の時間を入れることで、
予定通りにいかなくても心が乱れにくくなりました。
工夫④:「在宅や副業など、新しい選択肢を知る」を取り入れた
通勤・時間拘束のある働き方にこだわらず、自分に合う仕事スタイルをリサーチ
在宅ワークやクラウドソーシング、スキルシェアなど、今は柔軟な仕事スタイルが多数あります。



私は「子どもが起きる前に1時間だけ作業する」など、
自分のリズムに合う働き方は、思ったより多いと気づけました。
工夫⑤:「家族のタスクを“見える化”して分担」を取り入れた
結論:
家族にやってほしいことを、言葉や紙で“見える形”にしました。
理由:
「察して」ではなく「伝える」ことで、分担がしやすくなったからです。
根拠:
ホワイトボードに「明日の予定」や「今日やってほしいこと」を書いておくだけで、家族との連携がスムーズになりました。
自分ひとりで考えていたことを“共有”することで、精神的な負担も軽くなります。
今の生活を変えずに「働き方」だけを変えるメリット3つ・デメリット2つ


「生活スタイルをガラッと変えるのは不安。でも、今の働き方はつらい…」
そう感じている人に伝えたいのは、「生活全体を壊さなくても、“働き方”だけを見直すだけで暮らしは変わる」ということ。
ここでは、実際に私が感じた“働き方を少しだけ変えたこと”によるメリット3つとデメリット2つをご紹介します。
メリット
メリット① :通勤や時間のムダが減る
結論:
在宅勤務や短時間勤務に変えることで、通勤時間がゼロになり、心にも体にもゆとりができました。
理由:
1日1〜2時間の通勤は、見えにくいけれど大きな負担だからです。
根拠:
往復で1時間かかる通勤がなくなると、週に5時間、月に20時間、年に240時間もの余白が生まれます。
この時間があれば、子どもの話をゆっくり聞く、読書する、運動するなど、自分を満たす行動に使えます。
メリット② :子どもの急な予定に柔軟に対応できる
結論:
柔軟な働き方に変えたことで、子どもの体調不良や行事にあわてず対応できるようになりました。
理由:
自分で働く時間を調整できる仕組みがあると、「今日だけは無理をしない」という選択が可能になるからです。
根拠:
在宅ワークやフリーランスの仕事なら、「午前中だけ休む」「夜に仕事を回す」といったアレンジができます。
子育て期は予測不能な出来事の連続なので、働き方に“遊び”があると安心感が段違いです。
メリット③ :自分の「得意」や「好き」を仕事に活かせる
結論:
働き方を見直すと、自分に向いている仕事に出会える可能性が広がります。
理由:
職種だけでなく、働く手段(在宅・副業・業務委託など)を変えることで、活かせるスキルや価値観も変わるからです。
根拠:
たとえば、文章を書くのが得意ならブログ運営やライター、整理が得意なら家事代行やオンラインサポートなど。
「場所に縛られない働き方」に目を向けると、意外と自分の経験が役立つ仕事が見えてきます。
デメリット
デメリット① :孤独感や自己管理の難しさがある
結論:
在宅や一人作業が増えると、孤独を感じたり、だらけてしまう日もあります。
理由:
他人の目がない環境では、ペースを保つのに自制心が必要だからです。
根拠:
「誰とも会わずに終わった1日」が続くと、思った以上にメンタルが落ち込みます。
また、つい家事を優先したり、やる気が出ずに後回しにしたり。
予定を立てる、タスクを見える化するなどの工夫が必要になります。
デメリット② :収入が安定しない可能性がある
結論:
勤務形態や働き方によっては、月によって収入がばらつく場合があります。
理由:
特にフリーランスや単発業務では、案件の波や体調によって収入に変動が出やすいからです。
根拠:
ただし、これは“安定しない”のではなく、“自分でコントロールできる自由がある”とも言えます。
複数の仕事を組み合わせたり、固定収入のベースを持つことでリスクを減らす工夫が可能です。
「時間が足りない…」から抜け出した先に見えたもの5つ


ずっと「時間がない」と感じながら走り続けていた日々。
でも、“働き方”と“考え方”を少し変えたことで、自分の中に余白が生まれ、暮らしが少しずつ変わっていきました。
この章では、時間のゆとりを取り戻したことで見えてきた、**「大切にしたい5つのこと」**をお伝えします。
改善①:自分の気持ちに気づけるようになった
結論:
「忙しすぎて気づけなかった自分の本音」に耳を傾けられるようになりました。
理由:
時間に追われていると、感情に気づく余裕すら奪われてしまうからです。
根拠:
何となくイライラしていた理由や、モヤモヤの正体が、少し立ち止まることで言語化できるようになりました。
結果、「本当はこうしたかったんだな」と気づき、暮らしの軸を整えるきっかけになりました。
改善②:子どもとの時間を心から楽しめるようになった
結論:
「やらなきゃ」の気持ちから解放されて、子どもと向き合う時間に愛着が持てるようになりました。
理由:
気持ちに余裕が生まれると、「今この瞬間」に意識を向けられるようになるからです。
根拠:
ごはんを作りながら先の予定を考えたり、子どもの話を聞いていても頭の中は仕事のことでいっぱいだった日々。
でも、働き方を見直して少しラクになったことで、「あ、今ちゃんと見てあげられてるな」と感じる瞬間が増えました。
改善③:無理しなくても大丈夫と思える安心感
結論:
「がんばりすぎなくても、ちゃんと回る」ことを体感できたことが、自分にとって大きな安心になりました。
理由:
頑張りが習慣になっていたからこそ、「手放しても大丈夫」という感覚が新鮮だったのです。
根拠:
最初は罪悪感や不安がありましたが、「あれ、意外と回るな」と思えたことで気がラクになりました。
むしろその余白が、子どもや自分にとっていい循環を生み出してくれました。
改善④:社会とつながりながらも自分らしくいられる
結論:
働くことは、「自分を消して社会に合わせること」じゃなくて、「自分を生かして誰かとつながること」だと実感しました。
理由:
柔軟な働き方は、自分らしさを守りながら人と関われるからです。
根拠:
以前は「仕事=自分を押し殺す時間」でしたが、今は「自分の強みや好きなこと」で貢献できる時間に変わりました。
その変化が、仕事へのやりがいにもつながっています。
改善⑤:毎日の「小さな幸せ」に目を向けられるようになった
結論:
忙しさで見落としていた日常の喜びを、ちゃんと感じられるようになりました。
理由:
“追われる”生活から抜け出したことで、日々の中にある満足を受け取れるようになったからです。
根拠:
朝、子どもとゆっくり食べる朝ごはん。ふと空を見上げる時間。
そんなささやかな瞬間を「うれしいな」と感じられることが、今の私にはとても大切です。
【FAQ】よくある質問とその回答
- 自分に合った働き方って、どうやって見つけたらいいんでしょうか?
-
働き方を選ぶときは「今の生活で譲れないもの」を明確にするのが第一歩です。時間・体力・優先したいことを見直すことで、自分にとって無理なく続けられる働き方が少しずつ見えてきます。
- 在宅ワークに興味はありますが、パソコンが苦手でもできますか?
-
もちろん可能です。最近ではスマホ1台でもできる仕事もありますし、操作に不安があっても無料の学習サービスなどで基礎を学べば十分に対応できます。はじめから完璧を目指さなくて大丈夫です。
- 家族に「働き方を変えたい」と言うのが難しいのですが…
-
「〇〇をやめたい」より「こうしたい」という前向きな形で伝えるのがおすすめです。自分の負担を減らすことが、家族全体にとっても良い影響をもたらすという視点を共有してみてください。
- 急な予定や子どもの体調不良で、結局何も進まない日が続いてしまいます。
-
思い通りに進まない日があるのは当然です。大事なのは「できなかったこと」ではなく、「今日はこれだけできた」と切り替える視点を持つこと。日々の小さな前進を肯定することが継続のカギになります。
- 柔軟な働き方って、責任が軽くなる分やりがいも減るのでは?
-
やりがいは時間の長さではなく、自分の納得度で決まります。限られた時間でも「得意なことを活かしている」「誰かの役に立てている」と実感できる働き方は、むしろ満足感が高いと感じる人が多いです。
- 子どもが小さいうちは働くのを控えたほうがいいのでしょうか?
-
一概には言えません。大切なのは「どう働くか」より「どんな気持ちで暮らしたいか」です。働くことで気持ちが整う人もいれば、今は育児に専念したい人もいます。そのときの“自分軸”を大切にしてください。
- フリーランスや副業は不安定で怖いです。どう備えるべきですか?
-
不安定な面があるからこそ、いきなり一本に絞るのではなく「週に数時間」から始めてみるのがおすすめです。収入源を複数持っておくことがリスクの分散にもなり、精神的な安心感にもつながります。
- 毎日バタバタしていて、働き方を見直す時間すら取れません。
-
一気に変えようとしなくても大丈夫です。たとえば「1週間に15分だけ、今の生活を振り返る時間を持つ」だけでも大きな一歩です。自分の今の状態を言葉にする時間こそが、見直しの第一歩になります。
- 完璧を目指してしまい、働き方を柔軟にすることに罪悪感があります。
-
完璧さにこだわりすぎると、自分の限界に気づきにくくなります。柔軟にすることは妥協ではなく、持続可能にするための戦略です。「私が無理をしないことが、家族にも優しくできること」と考えてみてください。
- 自分の時間ができたら、何をしたらいいかわからなくなってしまいます。
-
“何かしなきゃ”と思わなくて大丈夫です。最初はただぼーっとする時間でもOK。それは自分をリセットする大事な時間です。無理に予定を詰め込まず、自然とやりたいことが湧いてくるのを待ちましょう。
まとめ


- 子育てと仕事を両立できているように見えても、心や体が疲れていると感じるのは「頑張りすぎ」のサインかもしれません。
- 「時間が足りない」と感じる背景には、名もなき家事や思考の切り替えなど“無意識の消耗”が積み重なっている可能性があります。
- 自分に合った柔軟な働き方は、ラクする手段ではなく、暮らしと自分を大切に保つための前向きな選択肢です。
- 自分時間を増やすには「完璧を手放す」「スケジュールに空白を入れる」など、小さな行動の見直しが効果的です。
- 働き方を少し変えるだけでも、心の余裕や家族との時間、自分らしさを取り戻すきっかけになります。